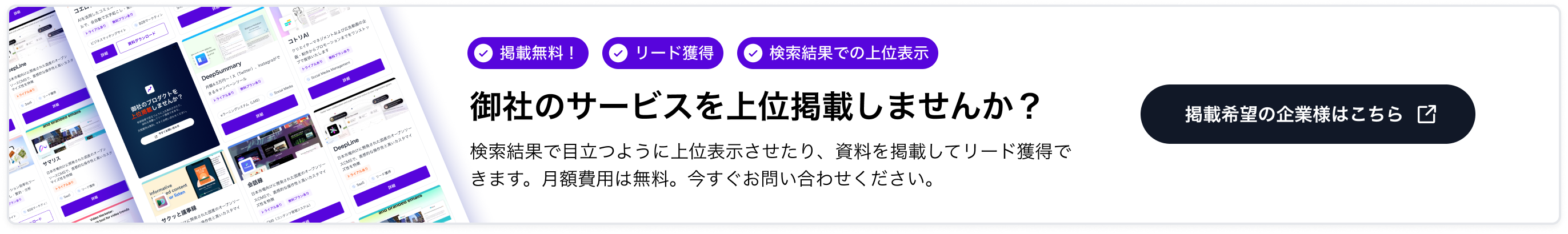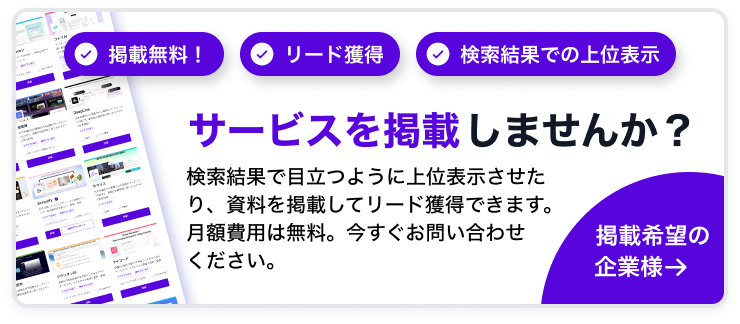AI文章と判定されないためには?不自然さをなくす改善テクニック
更新日:
ChatGPTやAIライティングツールの登場により、誰でも簡単に文章が作成できるようになりました。ブログ、SNS、商品説明、メルマガ……。これまで多くの時間をかけていたライティングが、驚くほどスピーディーかつ効率的に進められるようになってきています。 実際に、こうしたツールを使って記事を書いてみた方も多いのではないでしょうか。 しかし、便利な一方でよく読み返すと、「ちょっと不自然でAIっぽい」「似たような事ばかり書かれている」などの違和感を覚えたことはありませんか? AIは完璧ではなく、あくまで補助的なツールです。正しく使えば最強の武器になりますが、出力された文章をそのまま出せば、読者にAIっぽさを見抜かれてしまうこともあります。 この記事では、AIライティングの可能性と課題を整理しながら、AI文章と判定されないようにするためのポイントを解説します。
記事内で紹介されているサービス
目次
AIライティングの進化と活用シーン

ChatGPTやツールの登場で「ライティング」はどう変わった?
AIライティングツールの普及は、ライティングにかかっていた時間を短縮しただけではありません。これまで専門職の領域だった文章作成を誰もが取り組める業務へと変化を起こしました。これはライティングの役割やワークフローを根本から変えるきっかけにもなっています。
例えば記事の初稿作成をAIが行い、担当者が編集・仕上げをするやり方に変わった企業も多いのかと思われます。アシスタントのようにAIと一緒に思考を進めながら、共同で文章を完成させていくスタイルは、今後もさらに広がっていくでしょう。
特に中小企業や個人事業主にとっては、専門のライターにお願いせずに一定品質の文章が手に入るという点は、大きなメリットとなっています。
AIライティングが活用される主なケース
AIによる文章生成は、以下のようなケースで活用が進んでいます。
主なケース
- 1マーケティングコンテンツの作成
- 2顧客対応・カスタマーサポート
- 3社内文書・議事録作成
- 4商品説明やレビュー文の作成
- 5翻訳・多言語対応
これらはすべて、非常に時間がかかる業務でしたが、AIの導入によってコスト削減と生産性向上が同時に実現できるようになりました。
完璧ではない?AIライティングの限界

AIによる文章生成は、誤字脱字も少なく、読みやすいため一見すると高品質にも見えます。ですが、それゆえに印象に残らず伝わりにくいなどのケースがあるのも事実です。
そもそもAIは言葉の意味を人間のように理解しているわけではありません。深津式プロンプトで知られる深津貴之氏は、ChatGPTを入力した文章に対して「もっともらしい続きを書いてくれる」機械と表現しています(出典)。そのため、読み手の前提知識や感情、文脈に対する配慮が欠けやすく、結果として違和感を生じさせる原因となります。
すべてを任せる危うさ
AIライティングツールはあくまで補助的なツールであり、文章のすべてを任せきりにするにはリスクがあります。
たとえば、文脈を誤解した内容や、事実ではない情報が記載されていたりする事もあり、チェックをおろそかにすると、企業やブランドの信頼に関わる問題につながる可能性もあるでしょう。
さらに、情報が他サイトから引用されている場合、著作権や盗用の問題に発展することもありえます。
AI文章と判定されてしまうことも
昨今では、「この文章はAIが書いたものか?」を判定するツールや技術も登場しています。
大学や出版業界では、AIの利用についてガイドラインやポリシーも設けられており、提出された文章がAIによって書かれたものかどうかをチェックするツールも導入されています。
Webサイトやオワンドメディアのコンテンツ運用においてはAIで書かれた記事と判定され、信頼性や独自性を欠くと評価が下がる場合もあるため、文章作成後は必ず人の目による確認と修正・追記が必要です。
なぜ「AI文章」と判定されてしまうのか?

検索エンジンはAI文章をどのように評価しているか
GoogleはAIによるコンテンツ生成自体を禁止しているわけではなく、公式ブログでもAIを活用したコンテンツが役立つ場合もあると記載されています。
AI 生成によるコンテンツ作成を検討している方へのアドバイス
コンテンツの作成方法を問わず、Google 検索で成功を収めるには、E-E-A-T の品質を満たす、オリジナルで高品質な、ユーザー第一のコンテンツの制作を意識する必要があります。
※Google検索セントラルブログより:https://developers.google.com/search/blog?hl=ja
Googleがコンテンツの品質を評価する際に重視しているのが、「E-E-A-T」の原則です。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
AIが自動生成した文章であっても、これらの基準を満たしており、読者にとって有益で信頼できる内容であれば、検索順位に悪影響を与えるとは限りません。特に人間の編集が加わっている場合、SEO的にも十分に評価されるケースが増えています。
しかし、以下のような特徴を持つAI文章は、低品質と見なされ、検索順位が下がるリスクがあります。
- 他のサイトと酷似した内容
- 形式的な言い回しや一貫性のない論理
- 表層的な情報ばかりで深みがない
つまり、Googleが判断している点はAIが書いたかどうかより、その内容がユーザーにとって価値あるものかです。
「AIっぽい」と判定される文章の共通点
AIが生成した文章には、独特の癖やパターンが見られることがあります。これらは一見すると自然に読めるのですが、読者にはどこか違和感を与えてしまう原因となることがあります。
以下は、AI文章にありがちな特徴です。
- 全体的に画一的である:膨大なテキストデータを学習して文章を作り出すので、その特性上どうしても無難で汎用的な表現を選びがちになり個性のないものになります。
- 情報が表面的で深掘りできていない:AIは一般的な情報を提供することに長けていますが、特定の分野や専門的な内容に関しては深掘りが難しく、浅い内容になりがちです。
- 感情やニュアンスが伝わってこない:情報は正しいが、書き手の熱量や想いが伝わってこず、無機質で共感を呼ばない文章になりがち。
- 文体やトンマナに工夫が少ない:基本的な文法や構文は整っていても、読み手の属性や媒体の雰囲気に合わせた語り口の調整までは行えません。表現が単調で、どの文章も似たようなトーンになりやすく、読者の関心を引きにくくなります。
これらの特徴は人間が書いた文章とは異なる印象を与え、AIによって生成されていると判断される要因になり得ます。
AIライティングツールを使う際は、文章にストーリー性を持たせ、読者の視点から編集・調整することが重要です。これが、AIらしさをなくし、より自然な文章にするための効果的な対策となります。
不自然さをなくしAI文章と判定されないための改善テクニック

前述の通りAIが生成した文章には、画一的・表面的・無機質といった特徴が現れやすく、それが「AIっぽさ」につながります。ここでは、それぞれの課題に対して、どのように工夫・改善すれば自然な文章で伝わるものにできるかをご紹介します。
1. 画一的な表現から脱却するには?
AIの文章は、同じような言葉や言い回しを繰り返し使いがちです。これを避けるためには、語彙や構文のバリエーションを意識的に増やすことが重要です。例えば、「〜することができます」ばかりでなく「〜が可能になる」「〜を実現する」など、様々な表現を使ってみましょう。
また、比喩表現や例え話を効果的に取り入れることで、文章にリズムと個性が生まれます。これにより、読者は内容をより深く理解できるようになります。
2. 情報をしっかりと深掘りして書くためには?
AIは情報を効率的にまとめて記載しますが、深い洞察や独自の視点が不足しがちです。読者の「もっと知りたい」という欲求を満たすためには、一般的な情報だけでなく、具体的な事例・信頼できるデータ・独自の視点を積極的に盛り込みましょう。
AIが苦手とする背景を踏まえた解説や因果関係などの補足も意識して記載することで、文章に深みが増し、読者は物事の本質をより深く理解できるようになります。
3. 感情やニュアンスを伝えるためには?
読者からの共感や信頼を得るためには、書き手の立場や経験に基づいた語り口が不可欠です。過去の体験談を交えたり、読者の状況を想定した言葉選びを取り入れたりすることで、文章を「自分ごと」として捉えてもらいやすくなります。感情を込めた表現を用いることで、読者は文章に書かれている内容をより身近に感じることができます。
4. 文体やトンマナを工夫するには?
AIの文章はトーンが一定になりがちで、単調な印象を与えることがあります。これは、誰に・何を・どう伝えるかという前提が設計されていないまま文章が作られているためです。ターゲット読者を思い浮かべ、文章全体にどんな空気感を持たせたいのかを明確にし、それに沿った語尾・語彙・文調を意識的に整えることが重要です。文章の冒頭や結論に強調表現を取り入れたり、あえて口語を混ぜたりすることで、読者の注意を引き、飽きさせない構成に仕上げることができます。
これらのテクニックを実践することで、AIが生成した文章に人間味と深みを加え、読者に響く魅力的なコンテンツへと進化させることができます。
【厳選】実務に役立つ!おすすめのAIライティングツール5選
これまで紹介してきたようにAIが生成した文章を、より自然に・伝わる形へと仕上げるには、人の手による調整が不可欠です。しかし、これらのチェックと調整を手作業で行うのは、慣れない人にとっては負担が大きいものです。特に長文になればなるほど、一貫性を保ちながら全体を見直すことは簡単なことではありません。
そこで便利なのが、文体調整・構成補助・SEO観点の最適化などを自動的に支援してくれるAIライティングツールの活用です。これらのツールを上手に使いこなすことで、文章作成の効率が飛躍的に向上し、より洗練された自然な文章を短時間で仕上げることが可能になります。
以下は、実務でも使いやすくコストパフォーマンスに優れたおすすめのツールです。
BringRitera(リテラ)は、SEO特化のAIライティングツールで、ChatGPT-4を基にした記事生成を支援します。ターゲットキーワードに基づくコンテンツの迅速な作成と、専門知識を活かした情報提供が特徴。商用利用も可能で、ユーザーの権利を保護します。

料金プラン
月額費用
0円
フリー
月額費用/ユーザー
-
フリー
初期費用
0円
サービスの特徴は?
ChatGPT-4をベースにしたSEO特化型AIライティングツール
ターゲットキーワードを記憶し、見出しや記事を自動生成
網羅的な記事構成を提案し、読者に価値のあるコンテンツを提供
主な機能は?(できること)
多言語対応
タイトル生成
見出し生成
本文生成
テンプレート機能
参考情報の事前学習

トランスコープ
企業向けSEO特化型AIコンテンツ生成ツール
今すぐ
診断!
AI事例マッチ度
未診断
今すぐ
診断!
AI事例マッチ度
未診断
トランスコープは、シェアモル株式会社が提供するAIライティングツールで、企業向けにSEOに特化したコンテンツ生成機能を搭載しています。CSV一括生成、競合分析、リライト、コピペチェック、自動文字起こしなど、多彩な機能で効率的なコンテンツマーケティングを実現します。

料金プラン
月額費用
11,000円
Basicプラン
月額費用/ユーザー
-
Basicプラン
初期費用
-
サービスの特徴は?
CSV形式で数百から数千の情報を元に一括でコンテンツ生成
自社情報を学習してオリジナル性の高い文章を生成
URL・画像・音声にも対応するマルチモーダル入力
主な機能は?(できること)
競合キーワード抽出・分析
キーワード拡張
競合記事分析
タイトル生成
見出し生成
本文生成
どんな企業に導入されているか?
企業規模
小規模企業
1〜10名
中堅企業
11〜1,000名
大企業
1,001名以上
業界
主な導入企業
WEBBOX合同会社
三菱地所株式会社
レエール
ヨコイ塗装
CatchyはAIを活用した国内最大級のライティングアシスタントツールで、120種類以上の文章生成機能と企業のマッチングサービスを提供。使いやすさと質の高いマッチングにより、ビジネスチャンスの創出と効率的なコミュニケーションを支援します。

料金プラン
月額費用
-
Free
月額費用/ユーザー
-
Free
初期費用
-
サービスの特徴は?
120種類以上の生成ツールで、広告・記事・企画など多様なコンテンツを迅速に作成可能
ChatGPT搭載により、人間らしい自然な文章を自動生成し、ライティング作業を効率化
無料プランから始められ、プロジェクト数やクレジット数に応じた柔軟な料金プランを提供
主な機能は?(できること)
記事装飾
ペルソナ・ターゲット設定

Creative Drive
AI活用のパーソナライズドコンテンツ生成ツール
今すぐ
診断!
AI事例マッチ度
未診断
今すぐ
診断!
AI事例マッチ度
未診断
Creative Driveは、AIを活用したパーソナライズドコンテンツ生成プラットフォームで、CTRとCVRの向上を目指しています。継続的なパフォーマンス分析や多様なコンテンツ提供により、クライアントのマーケティング活動を効果的に支援します。

料金プラン
月額費用
-
月額費用/ユーザー
-
初期費用
-
サービスの特徴は?
独自の学習モデルに基づく高精度コンテンツ生成
継続的なパフォーマンス分析と改善
データドリブンなアプローチによる迅速な戦略見直し
主な機能は?(できること)
多言語対応
コンバージョンキーワード分析
ヒートマップ分析
コンバージョンタグ設定
記事作成代行
記事装飾
どんな企業に導入されているか?
企業規模
小規模企業
1〜10名
中堅企業
11〜1,000名
大企業
1,001名以上
業界
主な導入企業
learningBOX株式会社
株式会社STOVE
株式会社AdAI
SAKUBUNはAIを活用したライティングツールで、自動記事作成や編集、アイキャッチ画像生成、ペルソナ設定、共同作業機能など多彩な機能を提供します。マーケティングやコンテンツ制作に役立ち、作業時間を短縮しつつ高品質なコンテンツを生み出します。無料トライアルも利用可能です。

料金プラン
月額費用
-
月額費用/ユーザー
-
初期費用
-
サービスの特徴は?
記事作成を効率化し、100以上の生成ツールで最大70%のコスト削減
ペルソナ設定とSEOスコア機能で、ターゲットに響く高品質なSEO最適化コンテンツを生成
自社専用のカスタマイズ出力で、トーン調整や差別化された文章作成が可能
主な機能は?(できること)
見出し生成
本文生成
記事作成代行
テンプレート機能
記事装飾
AIモデル切替
よくある質問と注意点
Q1. AIで作った文章はSEOに影響しますか?
AIによる文章生成がSEOに不利ということはありません。ただし、Googleは自動生成された低品質なコンテンツを評価しないと明言しています。つまり、AIで作成したままの内容ではなく、人の手で編集し、読者にとって有益なコンテンツに仕上げることが重要です。
Q2. 著作権や法的な問題はありますか?
AIが生成した文章の多くは既存の情報を学習データとして用いています。そのため、生成された文章が他サイトと酷似してしまうリスクはゼロではありません。意図せず盗用にあたる可能性もあるため、オリジナリティの確保と確認は必須です。AIツールの利用規約や著作権ポリシーも事前に確認しておきましょう。
Q3. 社内でAIライティングツールを使う際に注意すべきことは?
AIに入力する内容に個人情報や機密情報を含めないことが基本です。特に無料版のツールは、入力データが学習に使用される可能性があるため、重要な情報はローカル環境や信頼できる有料プランで扱うようにしましょう。
Q4. AIライティングツールはどう選ぶと良いですか?
AIライティングツールは多様化しており、用途やスキルレベルによって適したものが異なります。選ぶ際には、まずどんな目的で使うのか(SEO記事、SNS投稿、商品説明など)を明確にしましょう。そのうえで、文章の自然さ・ユーザビリティ・カスタマイズのしやすさ・料金プラン・チームでの共有性などの観点で比較するのがおすすめです。
Q5. AIライティングと人間の役割分担は?
AIは構成案の作成や情報の整理などに優れていますが、誰に・何を・どう伝えるかといった企画意図の設計や、文体の微調整、感情の入れ方や、情報の深掘りは人間の領域です。両者の得意分野を分担することで、効率と質を両立した文章制作が可能になります。
まとめ
AIライティングの活用は、文章作成の効率を飛躍的に高めてくれます。しかしその一方で、AIっぽさが残ったままの文章は、読者や検索エンジンに違和感を与え、信頼や評価を損なう可能性があります。
AI文章を自然で読みやすい形に仕上げるには、語尾や構文のバリエーションを整える、接続詞や構成を強化する、具体的な表現に変換するなど、人間による編集が不可欠です。また、視覚的な整理や文脈・感情の補完によって、伝わる力が格段に高まります。
AIは補助ツールであり、最終的に伝えるのは人間です。効率と品質を両立させるために、AIを上手に活用しながら、読者に届く文章を仕上げていきましょう。
公式SNSをフォロー
最新のAIトレンドやリリース情報をいち早くお届けします。
今すぐフォローしましょう!
関連タグ
この記事の著者
O!Product編集部
「O!Product(オープロダクト)」は、日本最大級BtoBのAIツール・サービス検索サイトです。 「日本のすべての企業に、AIトランスフォーメーションを。」をミッションに掲げているGigantic Technologies株式会社によって運営されています。 AIに精通し、2017年設立時から企業のDX支援に取り込んでおり、十分な実績とノウハウを元に情報を発信しています。


あわせて読みたい特集・コラム
【2025年最新】無料で使える・日本語対応のAIライティングツールおすすめ10選!選び方と注意点を徹底解説